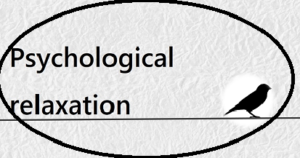当オフィスにおいては、心理カウンセリングを専門としておりますが、別途勉強会を企画しております。その中で、心身のリラクセーションを学ぶ「セルフケア勉強会」を随時実施してきました。
この勉強会は、対人援助職自身にも意味を持つものと考えております。
そして、合わせてここに別途新たなコンテンツを作成しました。対人援助職のためのセルフケア体験会としてまとめ、数種類の開催形式を企画しております。
様々な方式が考えられますが、緊張やリラックス、そして安心感に注目したケアを企画しております。
医療現場等でリラクセーションを用いた支援に取り組んできた経験を応用しています。
- セルフケア勉強会:こちらは対人援助職に限らず多くの方にご利用いただけるようなプログラムとしました。お二人でお越しいただいても結構です。
- ペアリラクセーション(企画中):こちらはまだ準備段階ではありますが、ペアでケアを行うものです。この方式が馴染むと、非常に可能性が広がります。
- 複数名でのワークショップ形式勉強会(企画中):コロナの影響も緩和されてきてはいますが、今のとこのオフィス内では3名程度が限度です。
案内をご参照の上、電話でご予約下さい。突然の訪問はご遠慮ください。
対人援助職のセルフケアについて
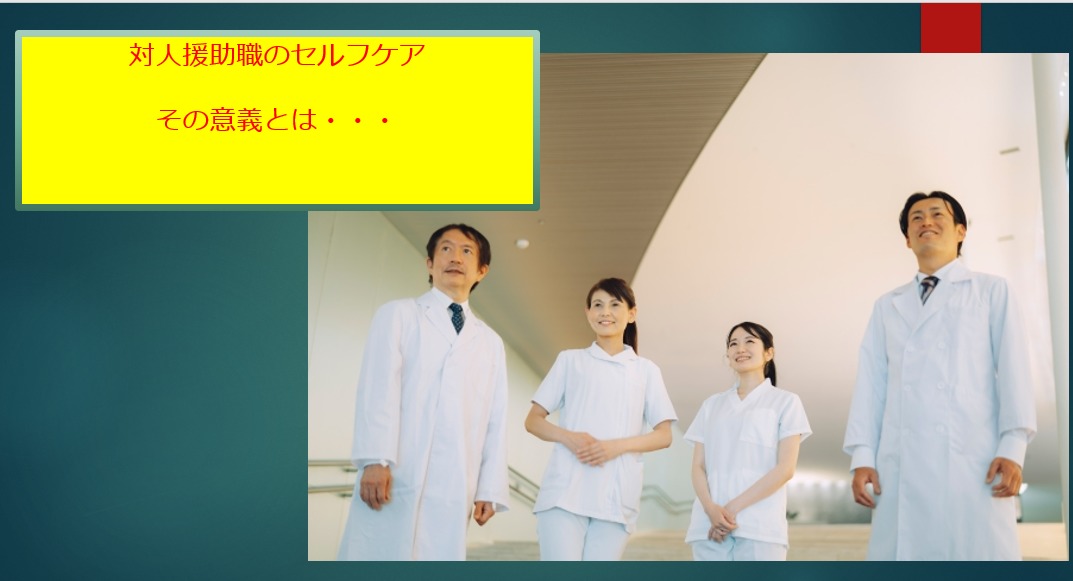
対人援助職のセルフケアを考えることには深い意義があると捉えております。
他者支援を専門とする者が、なぜ自分自身のケアなどに時間を割くのか?と後ろめたさをお感じになられる方もあるでしょうか。
援助職者が力尽き、倒れた後の支援は誰が担うのか

我々が直面する矛盾とも呼べる大きな命題は、援助職者が倒れた後、援助を受けていた人を誰が担当するのかという点です。
「別な看護師が担当します」とあっさり言える立場の方もあるかもしれません。
しかしながら、何人も倒れて行ったら最後には援助職者がいなくなり、支援もそこで終わることになります。
このテーマ自体が不謹慎ではないかとお感じになられる方もあると思います。援助職者自身のケアをする時間があるなら、患者やCLのためにこそ時間を使うべきであると、罪悪感を覚える方もあるのではないでしょうか。
その態度には敬意を払いたいのです。身を粉にして支援にあたる、本当に多くの尊敬できる対人援助職者を多数知っています。
そのような方が、道半ばで倒れて支援活動を中断せざるを得なくなるような事態を緩和できないものかと思いめぐらした時、こうした支援の重要性を認識するに至りました。
実はセルフケアが、支援を必要とする人を長く支えていくことになる
このように考えて続けてゆくと、どうやら支援者と支援を必要とする人は一蓮托生の如き関係にあるように見えてきます。倒れないように活動を続けなければならないのです。
つまり、支援者がセルフケアを行うのは、自分自身のためでもあるかもしれませんが、支援を必要とする人のためなのです。
もっと直接的に言えば、必要な人に支援を長く続けるためです。
余談になりますが・・・

コロナ禍、ごく少人数の屋外ランチの際、ある人は椅子を2メートル引いて膝の上に食器を置いて食事を共にしました。上記の写真のように、屋外でという考えは良かったのですが、テーブルも小さいため話し込んでいるとちょうどテーブルの上の料理に飛沫が落下するのです。
ここで感染したなら5日後に予約している方のカウンセリングを中止しなければならなかったからです。大げさな人と周囲の人は見た事でしょう。そのとき、その対人援助職者の体は、自分一人の物ではなくなっていたのです。
長期支援が基本
多くの場合、対人援助職者の活動は長期支援です。もちろん、1回限りのご縁という支援もありますが、多くの場合長い月日を共にする活動なのです。
10年がかりの支援を、対人援助職側が余裕を失ったことで、3年で支援を終了となると、残りの7年はどうしたものでしょう。
もちろん、人間ですからやむを得ない事情で突然の活動中止はあります。それはそれとしても、支援者側がセルフケアを行うことで、長い活動と変えることができるなら、大いにセルフケアを取り入れて良いのではないでしょうか。
セルフケアの意義

どこか、セルフケアに後ろめたい気持ちを感じている方は、このような視点を取り入れてご参加いただくのはどうでしょうか。
セルフケアを学ぶことが、更なるよりより支援を見出すためのきっかけとなることもあるものです。
臨床心理士の世界では、「傷ついた癒し手」という概念がユング派を中心に提唱されています。
確かに、我々は自分自身に意識を向ける時間を必要としているのかもしれません。
臨床心理士に限らず、保育士、看護師、ケースワーカー、教師など対人援助の職にある方にとっては応用の効く概念ではないかと思います。
その他
これらの活動は、当オフィスの「カウンセリング」の枠組みとは別に企画しておりますが、ご利用にあたっては、当オフィスの性質などをご理解いただけますようお願い申し上げます。
その他、地域支援の一環で「リフレッシュ・セッション」も企画しております。合わせてご活用ください。
下記画像をクリックすると、案内のページへ移動します。