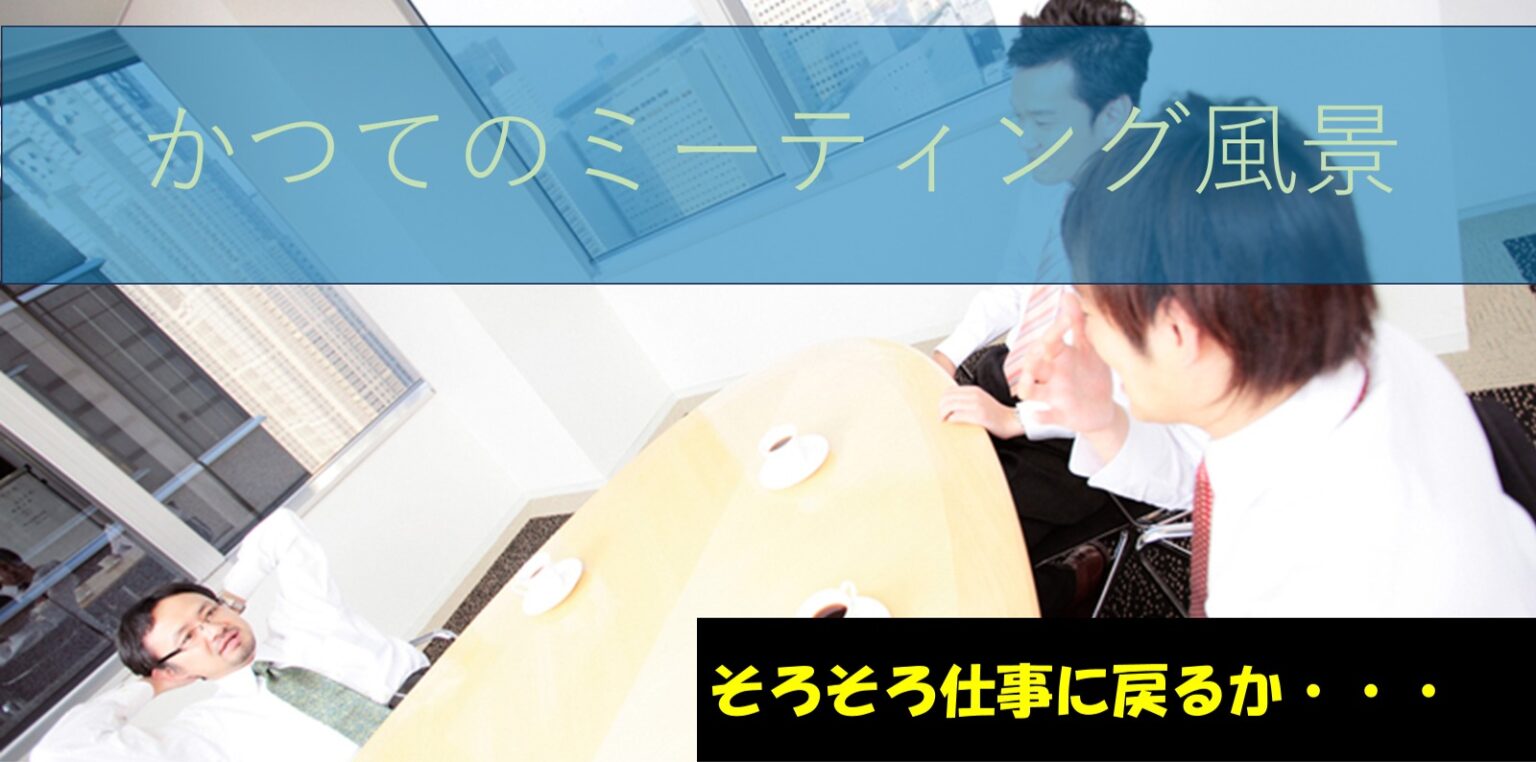昨今、IT機器の導入により1分単位で勤怠が管理される世の中になりました。
今から数十年前の世の中に生きた人は、なぜ一秒でも遅刻すると給与が引かれるのに、10分残業しても残業代が1円もつかないという矛盾に直面することがあったのではなかろうか。
果たしてこれは、吉と出たのか凶なのか、その検討もないまま社会は動き続けているように見えます。
確かに、残業時間はしっかり管理され支払われるべきだと思います。一方で、1分単位の世界とはいかなるものなのでしょう。
そして、世の中は働き方改革で残業を減らすように走り出しました。
労働密度を押し上げてくる

残業時間が減ったことは概ねよい傾向ではあると思われます。
一方で、残業削減実行前から懸念されていたのは、仕事が溜まるとか持ち帰ってしなければならないなどのことでした。
会社はきっと残業を削減した分、業務量も調整してくれるだろうと期待したいものですが、そうはならないだろうと多くの人が懸念していたのです。
カウンセラーの立場からすると、確かに残業が減るのはいいことに見えますが、やはりそう単純な事ではないと思っておく必要があります。
時間は短くなっても、皆で労働密度を上げて頑張ればやれる!

人は、何かの脅威に直面した際、いつも以上に気を引きしめて団結し困難に打ち勝つことがあります。
それは美しい様でもあり、一つの美徳だとも思います。
また、別な例えでは戦場での振る舞いがあります。
戦国時代の戦では、食料や薪などを温存しながら大事に使う必要がありました。無駄があってはならなかったのです。そして、常に心身をみなぎらせ研ぎ澄ませていたのです。
そのため、常に節約しギリギリ・スレスレの態勢で持ちこたえていたのです。
日常生活で使用する量よりも少ない物資で済むわけです。物事への集中して取り組んでいました。
転じて、いつでもそのような精神でいれば日々の暮らしも良いものになるのだと戦場の外にそれが持ちこされました。それを常在戦場の精神と言ったわけです。
- 別な線からも捉えられる話です:職場はやはり戦場なのか?同僚にうっかり気を許せない
これは我々労働者にも当てはまるところがないでしょうか。
繁忙期にはみんな一致団結して、集中的に業務に取り組み、いつも以上の力を出すものです。いつもの何倍もの速度で済ませる仕事もあったかもしれません。
そして、「よくやった」と上司は誉めるのです。
続けて、「やればできるじゃないか、いつもその調子でやるように!」と念押しするのです。
学校ならば毎日が試験3日前の緊張感を強いられるようなものです。3日くらいなら持つとしても、毎日それが基準になったら大変な事です。
残業の削減により弊害は、これに近いこと生み出している面が多少なりともないでしょうか。
そこまでやらなければ日本社会はまわらず、日本の戦略ということなのか!?

この意味するところは、早く帰れるのでもっと色々なことに時間を使えるという前向きな面があることは確かにあります。
これにより、家庭も明るくなるなどということもあったのでしょう。
もう一つには、今までは10時間で仕上げていた仕事を、きっちり8時間以内で仕上げなければならなくなったのです。決して、仕事の量が減ったわけではないのです。
残業は減っても、他の負荷が増えた、という結末もどうやらあるようなのです。
さきほどの家庭内のことにしても、早く帰った分新たな家事や役割が増えるということもあり、物事はシンプルではありません。
そして、「そこまでやらなければ、少子高齢化の日本社会はまわらない」という本音のようなもので締めくくられます。ここまでいくと、希望が見えずがっかりです。
「これが日本の戦略だ」ということなのでしょうか。
常在戦場というならば、洗濯は3日に一度にできないものでしょうか。そういう乗り切り方もあるでしょう。つまり、さらに向上するのではなく水準を維持ないしは落とすという戦略です。
- 関連ページ:こちらのページで少子高齢化社会の諸問題に言及しています 介護疲れ
現場によってかなり異なるというところがあると思います。
①全てを総動員、スリム化して臨まなければ維持できない現場、それから②残業がなくなってちょうどよくなった現場、③残業管理の数値にこだわって本質を見失った現場などに分けられるでしょう。
①はそうとうな労働密度になっていることが想像できます。②はゆるい職場などという言葉が登場してきたように、そこに該当するのでしょうか。③は訳が分からなくなっている感じです。
人は何時間くらいが集中的に働ける限度なのか
まず個人差や年代の差があるはずです。しかしながら、日本は一律で8時間労働が基本とされているかのようです。
いや、上限が8時間という方が正確なのではないかと思いますので、法律ギリギリまで目一杯働くことが基準という嫌味な言い方もできます。
学校の授業位に合わせるのはどうでしょうか。45分に1回休憩を挟めるのです。大学なら90分ですが、長すぎると言う人も多いのです。
8時間ぶっ通しで集中し続けるわけではない
8時間労働ならば、もちろんお昼休みが1時間程あるのが常識です。
概ね午前4時間、午後4時間ということになります。
5~6時間休憩なしで働くよりは、1時間の休憩を挟んだ方が負担は減りそうな感じがしますが、いかがなところでしょう。休憩がない分帰宅時間は早くなるので、それが良いという人もあるのでしょう。
いずれにしても、休憩は非常に重要な要素です。
- 関連ページ:上手な休憩の取り方とは
なんとなく仕事する時間が減った
業務中、お茶を飲めるかのめないか、これは大いなる違いではないでしょうか。
メリハリをつけるため禁止している職場もある訳です。
ここでいうお茶とは、小休止のようなことを言っています。
これがなくなって良かったという人も大勢いますが、労働密度はあがっていくのでしょう。
お茶を飲みながら同僚としばし談笑などというものがあるからこそ、仕事が終わらず残業する羽目になるのだ、という主張もあります。
この辺が悩ましい所のように思います。
しかしながら、かつては12時間でも働いていたという背景には、現在とは違う管理されていない時間がもっとあったという面もあったように思います。
情報過多・スピード超過な現代社会
また、この労働密度を押し上げているのは法律だけではなくIT化がかなり大きな要因になっている模様です。
いつまでも返事がなく、連絡を取るのがめんどくさいくらいのスピード感がちょうど良かったのかもしれません。現在ではリアルタイムなのです。
携帯電話の登場以降は、常に連絡がつかなくてはならない社会となりました。
ポケットベルが鳴ったら公衆電話を探す時代があった

その兆候はポケットベルの頃からありましたが。変遷を少し辿ってみます。
サラリーマンは会社の外へ出るとき、ポケットベルを携帯していました。
すると、ポケットベルが鳴るのです。これは会社に連絡せよとの合図なのです。
次に、公衆電話を探すことになります。

1990年代頃まではこんな感じだったのです。公衆電話を探すまで、多少の時間も必要でした。
その後PHSとガラパゴス携帯を持ち歩くようになっていきます。
すると、この会社との連絡体制はがらっと変わってきます。
出先でも課長と話して随時報告

携帯を持っていれば、どこにいても会社から電話ができるようになりました。「できるようになった」という響きは前向きですが、連絡が取れてしまうことになったのです。
ポケットベル時代であれば、公衆電話が見つからない・・・などと多少ごまかしてゆっくり時間をかけることもできたかもしれません。
今では地下鉄でも電波が入ります。
コンプライアンス重視されてなくなりつつあるかもしれませんが、頻繁に電話越しに怒りをぶつける課長もいたのでしょう。

そして昨今はGPSやテレビ電話も使うのですから、喫茶店でしらばっくれているようなこともできなくなりました。

もちろんいつの時代にも裏をかこうといする人はいるものですが、段々逃げ場を侵食されてしまいました。平気でたばこ休憩に出る人も久しく見ません。
このスピード感で仕事を求められるだけでも息が上がりそうです。実際、調査結果でも仕事の量に多くの人がストレスや不安を覚えていることが示されています。
都合よくやってくれたらうれしい
労働者にとっては面倒な事には目もつむり、1分でも残業した場合には支払ってくれる、そんな社会であったなら余裕が生まれるでしょうか。
現状、1分の残業に給与が発生する場合には、それと同じ分1分でも無駄にしてはいけないというプレッシャーを生んでいるように見えることがあります。
残業代をもらう権利をもらった代わりに、自由を売り渡せと言うかのようです。
「まさかそんなことはないよ!」とおっしゃる会社の方もいることでしょうが。
不確実な世の中においては、数字しか寄る辺がなく支配されているのかもしれない
コロナの2波辺りから、エビデンスとか、判断基準などという言葉が飛び交ったのを覚えています。
これに対して、曖昧にしている自治体と、はっきりとした数字を示す自治体とがありました。
どっちが良かったのかわかりませんが、曖昧な方は主観と言われても小回りの利くやり方でした。
数字で根拠を示した場合は、大丈夫そうな雰囲気であっても、数値が基準を満たさない限りは動きが取れないということになったわけです。
いつまでも便利にならない世の中
電動洗濯機や炊飯器の誕生は我々の生活を豊かにしたはずでした。
しかしながら、なんだかいつでも忙しい人がたくさんいるのはどういうことなのでしょう。
新たに生まれた分の時間はいつの間にか別なもので埋められてしまっているのです。
どこかで打ち止めにするという発想を持つことはないのでしょうか。
まとめ
数字で管理する事の他、もう一つには、その場の雰囲気や、その人の様子などを考慮するのはどうかと思うところです。
皆くたくたであることが目で見て明らかにわかる時、「さあ、あと10分時間が残っているぞ!」などと声をかけるよりは、「今日はこんなところだろ・・・」などと言ってくれる上司はいないものでしょうか。
クタクタの中、さらに10分位頑張ったところで大きな成果が出るとは思えないのです。
法的には問題ない、とか、基準を満たしている、などということが優先されるとき、もっとも単純なことを見落とす落とし穴が待っているように思うのです。
カウンセリングでは、おそらく可能な限りこの社会の流れと一体化し・取り込まれるのではなく、眺めて行くようなスタンスが求められるのだと思っています。
- 関連ページ:労働時間とうつ病等の関係について