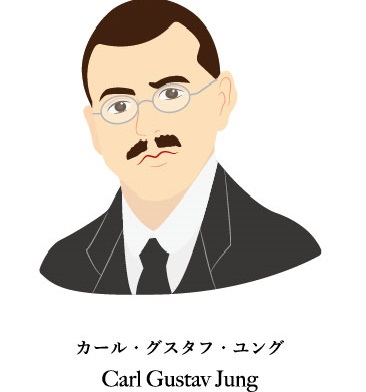ユングはスイスの心理学者で、分析心理学で知られています。(日本においては、ユング心理学とも言う)ユングは元々、フロイトのもとで学んでいましたが、途中から活動を別々にしています。フロイトに出会う前は、チューリッヒのブルクヘルツリ病院で、オイゲン・ブロイラーのもとで学んでいました。
ユングについて
フロイト同様に、心理学や医学の世界に留まらず、宗教学や民族学などの分野にも彼の活動は影響力を持ってきました。
※ユングの本を探して見つからない時、オカルトコーナーを探すと置いてある場合も。
集合的無意識
フロイトが、無意識を個人レベルのことと考えていたのに対して、ユングは、人類普遍のイメージがあるのではないかと考え、個人的無意識のさらに下層に、広大な集合的無意識の層を考えました。
シンクロニシティ体験

シンクロニシティという言葉も、ユング心理学に触れる中で出会うことがあります。
カウンセリングの中で、別な見方として、物事に対するある見方をご提示することはありますが、その見方を押し付けることは最も避けたいことなのです。
シンクロニシティとは、二つの出来事間にある意味のある一致のことを指す概念です。少し非科学的なのではないか?とお感じになる方もいるでしょう。
ある青年の体験
というような偶然が起きたときです。この青年は意識して木の下を選んだわけではなく、ましてその気がブナの木であることも知りませんでした。その木の下が最も落ち着いたということをこの青年がどう体験するかという点が注目されるところです。
このような体験のことをシンクロニシティと呼んでいいのではないかと思います。
※この体験談はフィクションですが、参考文献があります。そのまま引用ではないのですがほぼ引用です。
カウンセラーはきっと伝えたくなる
冒頭の方で、リフレーミングをテクニックと考えていないというようなことを書いていますが、もし上記の青年がカウンセリングに訪れて、上記の語りを聞いていたとしたら、カウンセラー側にも、この青年はやはりピアノを続けたいのではないか?とか、この旅行はそれを確かめるために必要なことであったとか、ブナの木がそれを示してくれた、などという連想が自然と生じてくるわけです。
きっとカウンセラーは<そのエピソードは、ただの旅行の話というだけではないように聞こえます。私には・・・>などということを伝えたくなるでしょう。
こうしたときに、意味のあるやり取りがカウンセラーと青年の間で行われ、青年が旅行に出かけたということに、別な見方を提示できるのではないかと感じます。
なぜ!?今さらという数々の出来事
さて、また別な話ですがこのタイミングでなぜ!?ということが数々起こるものです。
またフィクション仕立てですが・・・ある青年の話です。
その青年の家では自宅で商売をやっており、取引先の人が頻繁に出入りしていました。
そして、色々な話をして帰って行くのです。それは仕事の話ばかりではありませんでした。
青年はその人たちが何の話をしているかなどまるで興味がなく、テレビを見ながらフンフンと言っていたばかりだったのです。
しだいに青年は年齢を重ね、チェスにはまったということでした。
しかし同年代にチェスの趣味を持つ人はなく、孤独と不全感を覚える日々を送っていたのです。
そんなとき、取引先の一人が実はチェス教室に通っていたことをいまさら知りました。
そして猛烈にチェスの話に興じました。
10年は付き合いのある人でしたが、このときはじめて知ったのです。
いや・・・話には出ていたのかもしれません。気にも留めていなかったということなのかもしれません。おそらくそっちが真実なのでしょう。

このようなテーマは一つ一つ丁寧にお話を進める必要があるでしょう。ましてやカウンセリングにおいては尚更です。そうでなければ、きっと表面上のやり取りに終始する結果となるのではないかと感じます。
フロイトとの相違
根本的には同じことに繋がるのではないかとの考え方もされるようになっているようですが、ユング心理学の特徴としては、「目的論的」であることが挙げられます。また、ユング心理学は、フロイトに比較すると全体性ということに着眼があると言われれています。
もし、この二人の相違点を問われたなら、無意識に関する認識を挙げるのも一つの回答になることでしょう。もう一点挙げるなら、心的エネルギーに関する考え方の相違と言えるでしょうか。
ユング心理学の特徴をまとめておくと
- 集合的無意識:個人的無意識のさらに下層に人類共通のイメージなどを見出しました。
- 個人心理学:ユングの心理学をこのように呼びます。
- 元型:トリックスター、老賢者、グレートマザー、シャドウなどがあります。(関連ページ:私にはもう一つの人生があった?浮かび上がる「影」 )
- 目的論的:ユングの理論は目的論的と言われます。
- 個性化の概念も忘れられません
日本への紹介
日本へユングの心理学が本格的に紹介されたのは、1960年代後半に河合隼雄氏が帰国した後のことです。河合氏はスイスでユング心理学を学び、日本人ではじめて、ユング派分析家資格を取得しました。
当時の日本では、人間中心学派(ロジャーズ他)が頻繁に勉強されている最中であったと言います。いずれにしても、カウンセリングを学ぶ者にとってはユングに触れることは重要だと思います。
何年か前に放映された映画「危険なメソッド」
もう何年も前のことになりますが、フロイトとユングを描いた映画が放映されました。実際に見たことはありませんが、何かの情報番組で取り上げられていました。
どんな映画だったのかを調べてみると、2011年にイギリスとドイツの会社が協同で制作したようです。日本では2012年の放映とのことでした。
タイトルは日本語で、「危険なメソッド」です。(リンク先は、ウィキペディアです。)
一体、どんな映画だったのでしょう。映画の公式サイトを確認すると、許されぬ愛、などのキャッチコピーが見受けられます。かなりディープな内容なのかもしれません。こうした映画をみたら、フロイトと、ユングの違いも理解しやすくなるかもしれません。
フロイトやユングを演じた役者さんの写真が掲載されていますが、我々が心理学のテキストで見た姿とそっくりです。
まとめ
ユング心理学を理解するには、その著作を順番に全部読んでいくことだとどこかで聞いたことがあります。
コンパクトに理解できればとついつい願ってしまうものですが、そんな都合のいいことはありません。感性を磨くというカウンセリングと同じで、ショートカットなどなく地道な勉強が必要なのでしょう。
確かに読んで理解するプロセスはどうやっても必要なのだと思います。