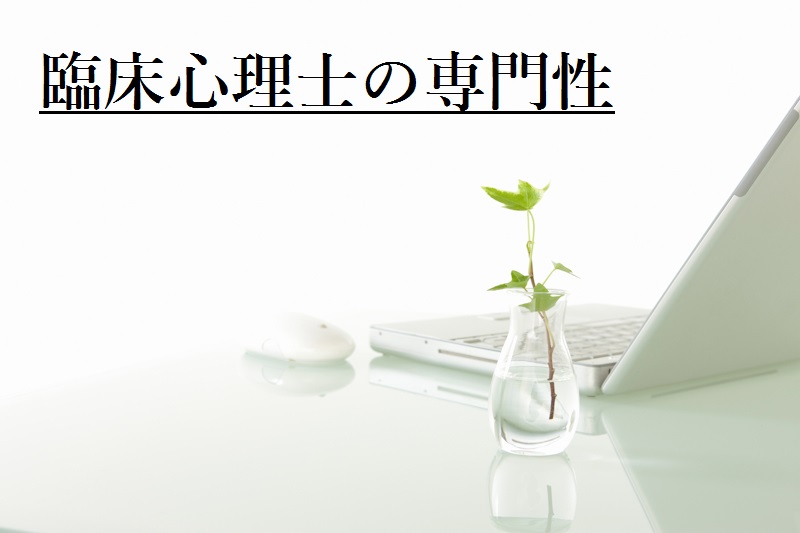現在カウンセラーの資格には特別この資格がなければカウンセリングを行ってはいけないという決まりはありません。勉強とトレーニングを重ねれば、独自に心理面接を行うことも可能とされています。
臨床心理士について
(公認心理師という国家資格ができましたが、今後もカウンセリングは公認心理師に限ったものではありません。
現在カウンセラーが最も多く働いている現場は、学校と病院現場が大多数を占めます。
では、資格を持っている場合、どのような人がカウンセリングを行っているかというと、多くの場合、臨床心理士という資格を持った人が従事しており、その数は段々と増えています。
4万人以上が取得した、大学院卒をベースとした民間資格
臨床心理士とは4つの専門性を掲げる民間資格です。
1988年に資格認可が始まり、現在万4万人以上の人が資格を取得するに至りました。
資格さえあればカウンセリングが十分に行えるかというと、決してそういうわけではありませんが、この資格を取得した人は、ある種の養成課程を修了していることを意味します。
詳しくは、臨床心理士資格認定協会のHPを見ていただく方が良いと思いますが、この記事でも簡単に触れております。
現在のところ、臨床心理士の資格を得るためには、所定の大学院で修士課程を修了することが条件になっています。
学部で何を先行していたかは関係なく、概ね指定の大学院での過程を修了することが資格取得の基本要件になります。
多くの臨床心理士は修士論文を書きつつ、指定の大学院で臨床的トレーニングを受けています。(1種指定大学院には、心理相談センターのような施設が設けられています。)
- 関連記事:大学院等附属のカウンセリング機関一覧
資格更新制度
臨床心理士資格は、5年で資格を更新する制度があります。5年間の内に、認定協会が定めた基準を満たす研修等に参加することが必須になります。つまり、資格取得後も継続して専門性向上のため研鑽を続けています。このことが制度として備えられています。個人では、認定協会が定める基準以上の研修の機会を得ようとする人も多くいます。
4つの専門性
臨床心理士には主に4つの専門性があります。
それは、心理面接・心理査定・臨床心理的地域援助・研究活動とされます。
心理面接
心理面接とは、いわゆる心理カウンセリングのことを指します。この専門性が臨床心理士専門性の中核ではないかと私は考えています。
基本的に1対1のカウンセラーとの対話の中で、より良い方向を共に探究していく作業と言うこともできるでしょう。
カウンセリングの方法は精神分析的アプローチ、人間中心アプローチなど様々ですが、他の職種が行う、「相談」・「教育」・「指導」とはまた別な専門性です。
心理査定
説明の仕方は多数考えられますが、医師が行う「診断」とは異なります。また臨床心理士に診断する権限はありません。では、何を行っているのかと言えば、「体験を理解すること」と考えています。それは面接形式で行われることもあれば、心理検査を用いる場合もあるでしょう。
臨床心理的地域援助
心理面接や、心理査定、その他臨床心理学観点からの様々な蓄積などから、個人だけではなく、集団に対する援助を行うことがあります。例えば、日々の活動の中でストレスに詳しくなった臨床心理士が、ストレス対策のプログラムを構築し、企業や学校などで役立てていただくことがこの活動に該当するでしょう。
- 詳細ページ:臨床心理的地域援助も行う
研究活動
幅は広いのですが、諸活動を通して浮かび上がってきた課題やテーマに関して研究を行うことがあります。例えば、ストレスを対処する方法を実践してきた臨床心理士が、大規模なストレスに関する実態調査を行い、数量的にまとめ、論文化するなどして、その傾向を明らかにするなどの活動です。
書9う歳ページ:研究活動
活動領域は幅広い
臨床心理士は医療機関と、教育関係機関に多く在籍しています。医療機関においては、各種の精神疾患を治療中の方の心理カウンセリングや検査を担当しています。また、教育関係機関においては、不登校などの支援を担う役割をもっています。
学校に配置されているスクールカウンセラーの多くは、臨床心理士資格を取得しています。そして、現在、その活動領域は非常に広くなっており、医療・教育をはじめ、司法・産業・福祉などの分野においても活動しています。
このように多様な領域に従事していますが、活動分野が異なっても、カウンセリングを行う際の、臨床心理士ないしはカウンセラーとしての一貫した態度が必要であると考えています。
資格の沿革
1988年といえば、どんな年だったでしょうか。
昭和63年のことになります。日本でも様々なことがあったことでしょう。2016年から遡ること、28年も前の事です。今、30才の人は、2才の頃の話です。千代の富士関が、53連勝を収めた年でもあります。実は、この年にカウンセリング関係領域にも大きな転機が訪れました、それが、臨床心理士の誕生でした。
心理士の資格化は、1988年より遙か以前から議論されていたのですが、ようやくこの年に誕生させることができたという経緯があります。本来は国家資格を目指していたのだと思いますが、民間の資格として活動を開始しています。(この資格が現在の公認心理師資格とも密接に関係しています。)
戦前に、心理カウンセラーという言葉が、日常用語の中に登場する機会がどのくらいあったものでしょうか。カウンセリングという言葉が、日常用いられはじめたのは、1950年代以後のことではないかと思います。
1950年代から、ロジャーズのカウンセリングが日本に紹介されはじめ、日本各地でカウンセリングを学ぶ人が増えて行きました。特に教育関係の分野で多く学ばれたそうです。
この頃から考えると、1988年という年は、35年くらい後のことになります。
この間にも、徐々に心理カウンセリングへの関心の高まりが増えて行ったのでしょう。
心理カウンセリングや人間の心理という面に意識が向き始めた背景を、物が豊かになったことと関係させて考えることがあります。
戦後の経済成長は右肩上がりで進んでおり、その当時はなかなか心理的なことに意識が向きにくかったのでしょうか。「もはや戦後ではない」が流行語になったのは1956年頃でした。この頃から、食糧難も徐々に改善されていったのでしょうか。
日本の経済は、この先長い事右肩上がりの中進んでいきました。
この右肩上がりの中で、どのように心理的な面へ意識が向いていったのでしょうか。この延長線上にも、心理士の資格化を進めた一つの理由があることになるでしょう。
1988年から増えて続け3万人を超えた
さて、臨床心理士は1988年に誕生してから、2016年現在でも活動を続けています。資格取得者は3万人を越えた模様です。→ 関連サイト:臨床心理士試験合格者人数の推移
今後、公認心理師資格の登場に伴い、こうした数値的なことがどのように変動するかはわかりませんが、日本の心理士分野の活動は、このような資格とともに進んでいくことになりそうです。
心理臨床の世界にはたくさんの先輩方が存在してきました。まだまだ現役で第一線に出ている方も数知れずいらっしゃいます。
1988年から30年以上が経過しました。国家資格が実現したとはいえども、重要なのは活動するその人自身の質ということになります。
先輩方から学ばなければならないこともたくさんあります。
あとがき
臨床心理士とは何か?と問われたら、「カウンセリングを行う者です」と答えたいと思っています。(カウンセリングを心理療法と言っても、心理面接と言っても通じます)もっと、美しい言い方はあるにしても、アイデンティティをそこに持っているという意味です。
ですが、そうではないとする意見やご批判もたくさんあがるでしょう。この20年の間に臨床心理士の活動はカウンセリングのみというには相応しくない状況となりました。
ですが、お一人でも、カウンセリングを担当することの重みは非常に大きいと考えています。そして、カウンセリングを行う人が増え、質を維持・向上していくことも当然永続的なテーマです。
臨床心理士は、一人一人と丁寧にお会いしていくことを旨としていたのはずではないでしょうか。